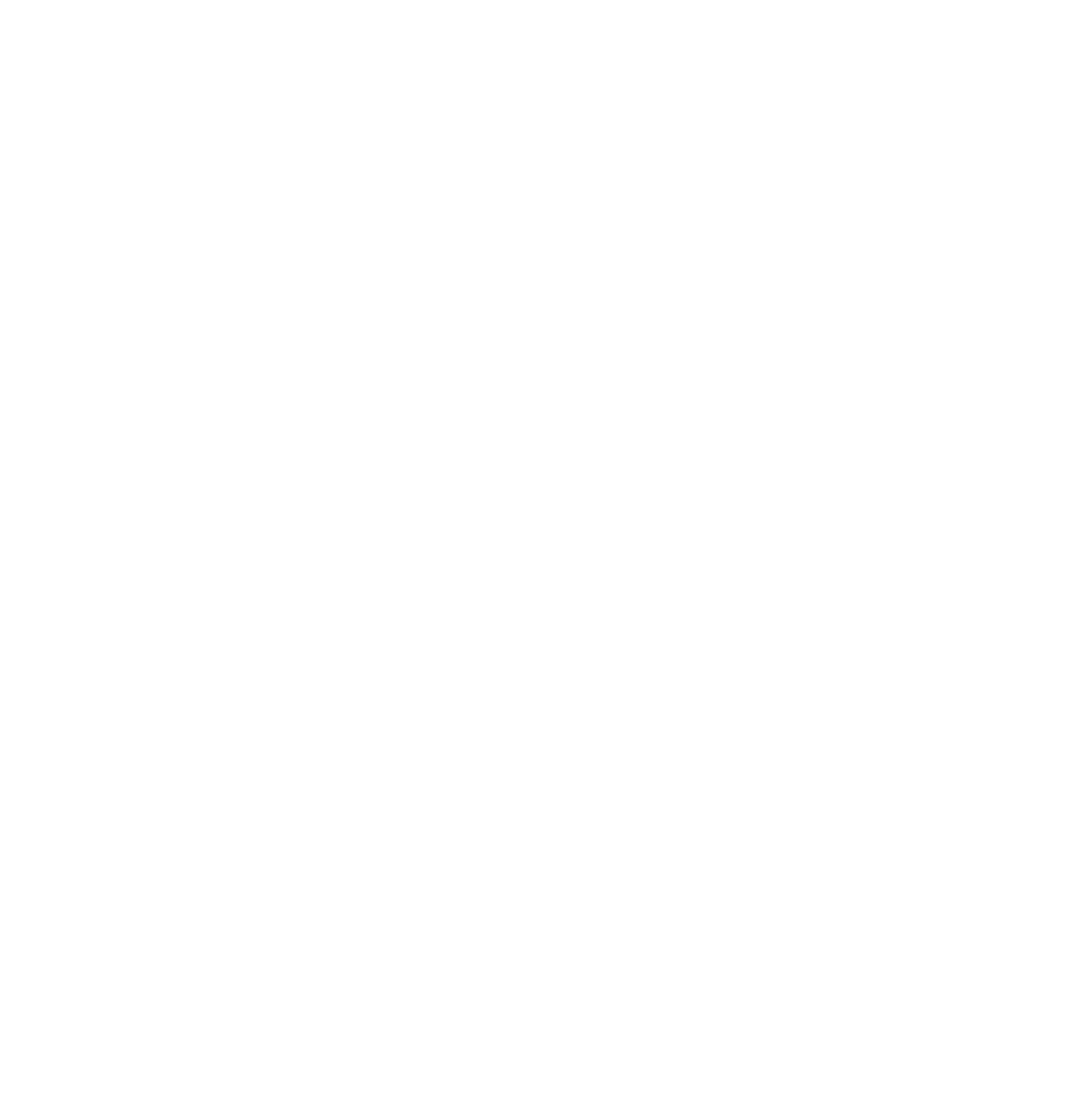田中泯とデレクベイリーのコラボパーフォーマンスを観たことがある。
田中泯というのは、田んぼの中でダンスを踊るというような既成概念にとらわれない独特のダンス活動を行い、世界的な評価をもつダンサーだ。
何年か前のNHK朝ドラ「まれ」で渋い塩職人のおじいさんを演じていた人という方がわかるかもしれない。
かたやデレクベイリーは世界的なギタリスト。本当にすごいコラボだ。
ただ、会場はとあるボーリング場。
前衛芸術全盛で、結構なんでもありの時代だった。
まずボーリングのボールをコロコロと投げて、そのボールが転がっているレーンの真ん中で田中泯がデレクベイリーのギターに合わせて踊る。
ここまでくると、もうようわからん・・・。
芸術というと、一部の見識ある人が理解するもの、なんか高尚なものと思っている人がいるかもしれないが、ボクは、あくまでも提供する人と受け取る人とのコミュニケーションと思っている。
音楽もまたしかりだ。ミュージシャンは自分の意思を音にしてオーディエンスに伝え、オーディエンスもまたそれを受け取って反応する。
ミュージシャンが提供するその意思は、オーディエンスの耳に慣れたものから前衛的なものまでいろいろだ。
前衛といったって時代を少しだけ先んじるものだから芸術たるのであって、たとえ少々わからん部分があったとしても、訴えかける力さえあればオーディエンスの心にずしんと響くはずだ。
これがただ単にわけわからんものであれば、演者の独善でしかない。
もっとも今世界のジャズファンに受け入れられ、支持されているパーカーだって、彼のアドリブは最初、「チャイニーズ・ミュージック(=わけのわからない音楽)」と批判されていたらしいから、難しいところ。
使い古された音ではない、一歩先行く音を提供したいとボクは模索する。
そんなことを話していると、スタッフが、「そういえば、田部さんの言うこと、ときどきわからないです。」と言った。
うーん、コミュニケーションは難しい。
BBコラム
「キタヨウ」と、ねずみ男はやってきた
町田謙介というミュージシャンの話をしよう。
ボクがアベベのマスターをやっていたときのこと、突然ねずみ男と名乗る男から電話がかかってきた。「僕は東京から来たねずみ男という者です。アベベで演らせてもらえないでしょうか。」
そんなことを急に言われても無理だというボクに、「ライブとしてではなくてもいいんです。せっかく小倉に来たんで、どこかでやりたいんです。」控えめだけど有無を言わせない物言いで、ボクは押し切られるように承諾してしまった。
彼との約束の日、ボクはコンサートのために日田まで出かけていて、正直に言えば、彼が来ることさえ忘れていた。
コンサートを終えて店に戻ろうと、階段を上っていたボクの耳に(当時アベベはビルの3階にあったのだ)何ともイイ感じのソウルが聴こえてきた。
「アレ?こんなレコードあったっけ?」
そう思いながらドアを開けてびっくり。見知らぬ男が歌っていたのだ。
日本人離れした太い声、ハンドクラップだけの演奏に、店のなかにいた10人ばかりのお客さんはノリにノッていた。
ボクはサックスを持ったまま、その場に立ちすくんでしまった。
「あぁ、そうだ。ねずみ男・・・、こんなに凄いヤツだったのか。」
そのあとボクたちは意気投合して、その日は店を閉めるまで2人でしこたま酒を飲んで、しこたま語った。店を出るとき、ふと不安になり、「どこに宿をとっているの?」と聞くと、宿は小倉駅だという。えっ?小倉駅に泊まるの?
彼の話によれば、冬は夜警のアルバイトをしてお金を貯め、夏は野宿をしたり、駅に泊まったりしながら全国を回っているのだという。
それならばと、ボクは遠慮する彼を無理やりボクの家に連れて行った。
翌日、ボクが目を覚ますと、彼はせっせと庭の掃除をしていた。泊めてもらったせめてものお礼という。一宿一飯の恩義?本当に気持ちのいいヤツだ。
彼はそれから3日間ボクの家に居候。一緒に飯を食い、夕方になれば一緒に店で演奏をした。本当に楽しい毎日だった。
音楽をしていて幸せに感じるのは、こんなふうに思いがけずいいヤツに出会えるから・・・とボクは思っている。
凄いよ、コンドー君
ボクは中学校のときにブラスバンドに所属していた。
賞を総なめにするとか、有名なミュージシャンを多数輩出したというようなクラブではなく、まぁごくごく普通の中学校の部活という感じのブラスバンドだった。
部員のなかにボクの同級生でコンドー君という子がいて、ある日「ムソルグスキーの『展覧会の絵』のなかの『キエフの大門』をブラスバンド用に編曲した」と言って、楽譜を持ってきた。
なんて生意気な1年生だと先輩たちは見向きもしなかったが(当時の部活の先輩と後輩との間には明確な力関係が存在したのだ)、顧問の先生がその楽譜をみて「やってみよう」という。
フツーの中学生だったボクは仰天した。若干13歳にして編曲とは。
それから部員一同四苦八苦してなんとか音を合わせることになる。と、これがなかなか良い感じなのだ。本当に凄い奴がいるものだと思った。
コンドー君は、「小学5年のとき、東京芸大の入試課題曲をマスターした」と豪語していたが、彼の音楽に対する意識というか態度は、音楽に対する概念をひっくり返すほどの影響をボクに与えたと言っていい。
彼は、中学2年の夏休み、「コラール集」という小冊子から数曲、4つのパートからなる楽譜を書いてきた。
少ない部員を4パートに分けて、コンド-君がオルガンでそのハーモニィを弾き、音程を合わせて練習するのだ。
たった8小節の楽譜から醸し出される教会風の荘厳な響きにボクは感動した。
その年の秋に彼は東京に転校して行った。
彼とはしばらく文通をしていたが、彼の手紙には決まって音楽のことが書かれていた。楽譜が書かれていて、モーツァルトの協奏曲のモチーフですという手紙をもらったこともある。「ミニスコアは勉強になります。」との手紙に、ボクもコンド-君に負けじと勉強した。ボクの読譜力が飛躍的に伸びたのはコンドー君のおかげだと思っている。
コンド-君は、音楽大学には進学せず、東大を出て、なんとかという研究所の所長になったという噂をきいた。
やっぱり凄いよ、コンド-君。
BBコラムTOPにもどる
ワタナベ先生のこと
ボクは中学校のときにブラスバンドに所属していた。
3年になって部長になったボクは、新入部員を50名入れるという計画を立てた。
まずはたくさんの人にブラスバンドのよさを知ってもらわなきゃ始まらないと思ったからだ。
一生懸命勧誘して何とか50名入部を実現させた。ボクの音楽への関わり方はいつもこんな感じだ。
体育会系のノリで、下級生を鍛えに鍛えた。今だったら、パワハラで訴えられるかもしれない。
中学校を卒業しても週に何回かは中学校に訪れ、指導を続けた。それ以外の日はボクのあとを継いで部長になったボクの弟にあれやこれやと指示した。
自慢するわけではないが、ボクの指導のもと弱小ブラスバンドはそこそこの演奏をするようになっていた。
コンクール出場が決まり、ボクは意気込んでいた。
「コンクールに出る以上は優勝したい。」
それは、ボクの夢であり、今まで頑張ってきた部員たちへのごほうびだと信じていた。当然ますます指導に熱が入る。
ところが、残念なことにコンクールは指揮者にいたるまで学校関係者でなくてはならなかった。中学校を卒業したボクは完全に部外者ということになる。
指揮をしてくれる人を捜していたところ、白羽の矢が立ったのがワタナベ先生だった。ワタナベ先生は音楽に造詣が深いということを聞いていた。
コンクールまでにあと少しという時期、仕上がり具合を見に行ったボクは、衝撃的なワタナベ先生の姿をみることになる。
ワタナベ先生の指揮は、指揮をするというよりまるで踊っているようだった。今までボクが必死で作ってきた形が崩れてしまう、なんてことをしてくれるんだ。これじゃコンクールで優勝することは無理だ。ボクは本気で腹を立てていた。
しかし、ボクにはなすすべがない。どこにもぶつけようがない苛立ちを抱えながら、コンクールの当日、ボクは会場に出向いた。
順番が来て、演奏が始まり、いつものように踊る先生の姿が目に入った。
その瞬間、ボクの体に電気が走った。
「心から楽しんでいる」そんな雰囲気が、先生から、演奏する生徒たちから感じられて、ボクは涙が出るほど感動してしまったのだ。
残念なことに、優勝は他の中学にもっていかれたが、ボクにとってそんなことはもうどうでもよくなっていた。
スポ魂が大嫌いだったワタナベ先生の「楽しまなくちゃ。コンクールのための音楽じゃつまらない。」という言葉が今でも心をよぎる。
今思えばワタナベ先生もそうした心境に至るまでいろんな思いをしたのかもしれない。
今でも弟と中学時代のブラスバンドのことを話していると、必ずワタナベ先生の話になる。「会いたいなぁ。」
ある日弟からワタナベ先生の消息がわかったと連絡があった。
残念ながら、数年前に亡くなられたという。
「先生の教えをきちんと守り、伝えています。」
そう先生に伝えたかった。
BBコラムTOPにもどる